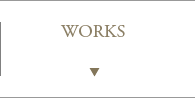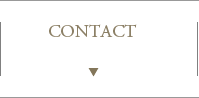かなりの時が経っていた。二人は長いこと熟睡したらしい。ほの暗い部屋の中ではオリーヴの油香が漂っていた。ローマの夏のなおも厳しく射るような西陽は、緑色の両開きに開閉する木組みの日除け扉(ブラインド)から闖入して、ストッカ(漆喰)の高い天井に縞状のアラベスク文様を映し出していた。遠く近くに打ち出した聖堂の鐘の音が建物の壁や広場に反射するのだろう。青銅と石の響きあう高らかで乾いて美しい音の調べがローマの低い屋根を渡っていく。聖ジョヴァンニの城門の辺りで、ひと際割れるように空気を震わせているのがラテラーノ大聖堂の鐘に違いない。ミサ{礼拝}の時を知らせているのだろうか、ただ時を拍っているだけなのだろうか。二人は鐘の音の細くなりやがて夕立の雨足のように立ち去っていくのを静かに聴き入っていた。
小声に男は口をひらいた。「グラーチア・・・そう言ったね、君の名、シチリアの出身(で)だったね」「・・・・・」、女はすぐには答えなかった。やおら、頭の後ろに回して組んでいた手をほどくと、男ノ顔を見やすいように静かに向きを変えた。まだ熟するには早く淡く色ずき始めた初夏の果実のような瞳と胸を大きく広げるようにしながら、片手で黒い髪を頭の後ろにたわめるように掬いあげて腋(わき)を露わにさし出した。・・・「ええ、シラクーサの田舎(プロヴィンチャ)よ、遠く碧い海を見下ろす丘の斜面にある邑だわ・・・オリーヴの樹葉が波打つだけの・・・」「・・・・」「オレンジの花も季節には咲くわ、レモンの木が男の拳(こぶし)程もある大きな実をつけるの・・・、近くにベルヴェデーレというありふれた名前の町があって、そこからの眺めは格別だったわ。海やシラクーサの町や遺跡が、夏の夕暮れオリーヴ園の向こう側で真っ赤に焼けるようにひろがっていたわ・・・」、ひっそりと囁くように答えた。シチリアの女は物静かだった。凪(な)いだ岸辺に浮かぶ小舟の船底を叩くさざ波のように囁いた。「・・・君の肌に潮の香がたっている。」、男はオスティアの海辺の砂丘に寝そべっている様な気分になって女の黒髪を五本の指で掬い上げていた。女の肩から胸へ,柔らかい脇腹から腰の隆起を伝ってゆっくりと撫でていた。そして再び目を閉じた。こうしてまだ訪れたことのない遠い南の島の夕映えの海を想い描こうと試みた。「グレーチア(ギリシャ)に近いんだね。僕のマエストロはシラクーサからそう遠くないカターニャの生まれだった。遠い昔、祖先はグレーチャから渡ってきたのだと言っていた。・・・どことなく君に似ていてね・・・」、実際マエストロはロマーノ(ローマ人)の様に分厚い胸や、短い猪首をしてはいなかった。声高く感情をあらわにすることも、誇張した手振りや身振りで喚きたてることもなかった。物静かで優雅でありながら、小柄な体の奥に脈打つ熱い濁りのない血をひそませていた。
「グレーチア・・・」、女の遠い所で反応が起きたようだった。渚(なぎさ)のさざなみが呟く様に思われた。「・・・グレーチァね・・」、男の掌がグレーチァと声を忍ばせた女の唇の方に伸び二本の指拇でそっと這うように触れた。温かい吐息が軽く指先を包んだ。「そうだったわ、幼い頃、黒い衣装に身を包んだ祖母が言っていたわ。オリーヴの香油で体を綺麗に拭きあげて呉れながら・・・可愛いグレ―チァ、どんなに貧しくてもこれだけは忘れないで守るのよ、オリーヴと太陽と潮風が肌をすべすべに綺麗にしてくれるのだよ。世界中で一番美しい肌をした乙女になるのだからね」、女は少し誇らしげな気分になって男の手を執ると自分の方に誘った。口元が微笑んでいた。「つまり君もグレーチアの血をひくシラクーサの女というわけだね」、「そうよ、きっと、・・・村に遠い昔にグレーチアから伝わった慣わしって、祖母はそう言ってたわ、それに村にはそんな慣わしが他にも幾つかあったわ・・・でも貴方ってグレーチアという言葉にこだわるのね、何故?」、女の囁く声の中にそれまで深く眠っていた好奇の心が急ぎ目覚めているように思われた。「ね、・・何故なの?」男は閉じていた目を見開いた。しばらくの間、女のおぼろげな顔の輪郭を遠くから眺めるように見ていたが、言葉をたぐるように語り始めた。・・・「解ってくれるかな?グラーチア、或る年の冬の昼下がりのことなのだ。ナポリの美術アカデミアの筋向いにある(国立考古学)博物館でのアフロディテの彫像に出会った時のことだ。シヌエッサのヴィナスと呼ばれていてね、とても魅惑的な女の裸像だった」・・、「グレーチア」の女体像という訳ね、一目で好きになったの?・・そうでしょう。そのシヌエッサ「お前みたいに!」とでも私に言ってみたいのでしょう。そうに違いないわ」、女の黒い瞳が男の目の中を訝しげに覗いた。男はかまわず続けた。
そのアフロディテの像は明かり取りの窓のある大きなギャラリーの西側の壁を背にして立っていた。丁度冬の陽ざしが雲間から顔を出して、いっとき部屋の中を明るく照らし出した。するとどうだろう。灰色の空気の中に沈んでいた大理石像の肌目に残照が映えて淡紅色に染まっていたんだ。まるで湯上りの乙女の肌のように豊麗に輝き出したのだ。幽明の境に燃えたつ炎の様に思われた。恥じらうように腰から下は今にもすり落ちそうな薄衣に包まれ、それも申し訳なさそうにね・・・、しかも薄衣の端を摘んでいるはずの腕も手指も欠けているのさ。きっと初めからつまんでなんかいやしなかったんだ。恥じらいながらも誇らしげに僕の前に立ちつくしている。豊かな量感の中に自足して不動なのだ。それに僕を見詰めているはずの瞳がない。頭部が欠けているのだね。僕は欠けている部分にシヌエッサの微笑みを探し求めていた。すると視えてきたのだね。・・・“ああ、シヌエッサ”そう呼びかけると思わず僕は動いてしまった。それまでは魅惑の女人をただ見詰めるだけだったのに」・・、傍らの女は瞬きもせず聞き入っていた。「それからどうなったの、貴方の体に火がついておかしくなったというのでしょう。きっとそうよ。そしてこの掌でシヌエッサのバラ色の肌に思う存分触ったのでしょう。その唇をだいじな所に重ねたのでしょう。・・・解るわ、顔を失った女を愛撫したという訳ね」、女の瞳の奥で黒くゆらめき、ちらちら燃えるものがあった。男は薄暗がりの中で思わず頬の赤らむのを感じた。人生の二十代の半ばを越えたばかりのその男のどこかにまだ少年の名残があった。「うん、部屋には僕以外に誰も居なかったんだよ。それで今こうして目を閉じて君の肌に触れているように・・」、女は差し出された手を握りしめると自分の胸に置いた。「変な人だわ、男って想う女の影を慕って私を抱きにくるのよ。欲しい女(ひと)、別れた女への未練もあるわ、でもそれはいつも誰かでしょ。その誰かを私に求めて来るわ、でも貴方は違う、どこか違ってるの。何故か怖いわ・・、貴方みたいな男(ひと)」。最後のひと言が正直、男には痛いほど突き刺さった。
思えば、男はかたくなに抱いている思念というもののためには、危険を冒し多少の犠牲を払ってでも諦めるわけにはいかないと思っていた。むしろそれを試練として立ち向かわねばならないと感じていた。とはいうものの、心の中では自分ならぬ他人をも手ひどく巻き添えにしてしまった苦い過去を忘れ去るわけにはいかなかったのだ。
女は一息ついて続けた。「私、そんな時、本当は体も心も石になろうとするのよ。柔らかい無感動の石だわ、なされるがままのことよ。時折まるでクラゲみたい。でも石であることには変わりないわ。感じてるふりをすればすむことよ。でも貴方は変わった人、怖い方よ。始めから石を抱くように私を抱いていたわ。愛撫しながらシヌエッサのこと想っていたのね。・・・あの大理石のヴィナスが熱く濡れてくるのを本気で待ち続けていたのよ・・・」、女の声にどこか鼻にかかる悲哀の翳りがあった。男は女から目を外すと天井に映る夕方の薄れ行く光彩を眺めながら言葉を探した。ローマは暮れようとしていた。その澄明な灰紫の暮色が女の哀切に変わっていた。
「でもね、グラ―チア、君と知り合うずっと以前から、僕はどんな女にもまして大理石が、暖かい肌や熱く柔らかい肉や骨格を宿した生きものであることを知っていたのだ・・」、「嘘、そんなこと変だわ!」、「いや本当さ、例えばスペイン広場の大理石の階段、知ってるだろう。僕は眠れない暑い夜、あそこに行っては仰向けに寝そべるのだ。果てしない夜空に銀の光芒がヴァティカンの聖火のように漂っている。星が幾つも降ってきそうだ。足下では広場の噴水がチロチロ音をたてている。コンドッティ街は夜の深い谷間だ。そうしていると背中から伝わってくる分厚い石の熱気が肌を透し肉を包み、骨の髄までとろけるように暖かく柔らかにしてくれる。心が塞(ふさ)ぎ哀しい時でも、深く広いものでゆったりと包んでくれる。ジーンと胸がしびれ思わず涙がこぼれ、頬を伝って乾いた石床を濡らすことだってある。なんだか解らないが身も心もいいようもない深い官能の震えに抱かれる。しかもそれに加えて背筋がビーンと伸ばされている。これもよくは解らないが何か強くて途方もない精神の在りようを予感させる何かなのだ」。「官能と精神が結びついている、と云うわけね。いい話だわ・・」、
女の表情に少し明るさがさしてきた。「でも寒い冬はどうなの、体の芯まで凍えるでしょうに・・・」「そう、死の床さ、実はそこが肝心に思える所なのだが、・・でも今は夏だよ、君も真夏だ」、「死の床ですって、それが肝心な所ってどういうこと?私、気になるわ、とっても気になるの・・・ちゃんと説明して欲しいわ、」話を逸らされると思ったのか、女は真顔で求めてきた。男はもっとましな言葉の筋道をたどろうとおもった。「・・・つまり、それだけが総てじゃないというわけだね…本当はというと、その同じ石はとうにどこかで人間様を突き離している。人間の感覚とか官能、肉体とか生命なんてどんなにか他愛ないものであるか、いやという程教えて呉れるのだよ。感覚や官能をさんざ刺激しておいて肉の歓びへ深いところで誘っておいてだね。刹那と永遠がその時ばかりは背中をすり合わせ狂わんばかりに愛し合っているようなものだが、心はもうどうしようもない程突き離されている」、「そうね、なんだか悲しいことなのね。でもどうしようもないことでしょう」、女は男の語りごとをかなり落ち着いて受けとめている様子だった。「実際、僕が寝そべっている居心地の良い同じ石の処だって、かって見知らぬ何人もの人達が来て横たわったことだろうか、外国の女王だっていたかも知しれない。僕がそこで感じたように感じ、僕がそこで考えたように考えたことだろう。僕にはそれが解るような気がする。だがその人達はとっくに逝ってしまった。此の世に居はしない。もしかしたらローマの乾いた暑い空気になって今頃石の面(おもて)を吹き撫でているのかもしれない。兎も角、石は昔のままに残っている。いっぱいの人がひと時そこにとどまり歓びそして消えていった。それが誰であろうと石にとってはどうだっていいことなのだ。石は沈黙して語らない。だが人間の歓び、悲しみ,儚(はかなさ)を見てきた。僕もだんだんそれでいいのだと思うようになってきた。そうである他(ほか)ないのだよ。ローマの街の全てが「そうだ、そうでしかないのだ。それでいいのだ。」そう言って夜更けの空に昂然と高笑いするのだね。聴こえてくるじゃないか!」「聴こえてくるわ、夜更けに露地を歩いていると足裏の石畳が同じこと囁くわ」、同感を込めて女は応じた。
「そうだろう。グラーチア、テヴェーレの流れだって同じことだ。ミルヴィオの橋(ポンテ・ミルヴィオ)、渡ったことあるだろう。あんな美しい石の橋なんか滅多にあるものじゃない。もう二千年近くも在るのだ。下をのぞくと流れる川面に自分の姿が映っている。今も昔も変わることなくアーチの姿影を水面に落としている。その手すりの端に僕はチョコンと佇ずんでいるのだ。すると二千年の想いに胸は締めつけられる」、男は思わず息をのんだ。目の前で女の貌(かお)が暗がりの中に冴えるように美しく浮かび上がった。その貌はアーチの形状に囲われて川面の奥からすっと現われてきたと思われた。「そうだわ、人も時も流れと共に逝ってしまって決して帰ってこないのよ。ミルヴィオの橋だけがいつまでも川面に姿を映しているもの・・」、妖しく愁いを帯びた声だった。その顔をじっと見詰めながら男は昂ぶる心を抑えるように言葉を継いだ。・・・「美しいローマ・・朧たけてあまりにも美しいローマ、チッタエテルナ(永遠の都)!・・不滅の娼婦よ!・・・素顔のままに恐ろしい程の魅力だ、底無しに瞬間を楽しませて呉れる。
それも身も心も魅せられて生の充満する瞬間々々を、永遠と死をたっぷりと見させてくれるのだ。背筋の歪みを許さぬ石床は底無しの魅惑の淵に立つ僕たちに厳かに語りかけてくる。――快楽を貫け、おまえの人生にそれ以外何がある。歓びも苦しみも悲しみも所詮、生も死もここでは同意義なのだ――。ぼくは一瞬ユピテルの声を背後に聴く思いがする。するとどうだろう。西の夜空にひと際巨大な影を沈めるサン(聖)ピエトロ寺院のクーポラ(大円蓋)が『「その通りだ。余に異存はないぞ』、とそれに応じるように勇ましい大音声を発している。
グラーチア、僕はこのローマが好きなんだ。どうしようもなく好きなんだ。深情けだろか?・・・君もそうした女かも知れない。ローマ、そんな女が外の世界の何処に居る?大理石像にも等しい快楽の重い十字架を背負ったローマ・・・」、「解ったわ、私だんだん解ってくるようだわ、だから貴方は冷たい大理石像を熱くしたかったのね。そうだったのね。本当にそうだったわ、私、しまいにとめどなく融けて蜜みたいになってしまったのよ。そうやってグレーチァの夜を想っていたのでしょう、アフロディテの夜を、それが貴方にとっての永遠の現姿(いま)というわけなんでしょ?変わった人だわ、本当に変わった人だわ、でも許されるような気がするの・・・、許されるわ!」女の言葉はそこで途切れた。両の瞳が燃えながら黒く濡れていた。白い額に乱れる髪は蒼く豊かなうねりとなって胸本を伝い胸から床に消えていた。
男は優しく大きく女を抱きながら軽く目を閉ざした。すると女の愛おしさが深かぶかと男の胸に広がり、女は背をすぼめぴったりと寄り添ってきた。
ひときわ強くオリーヴの油香が薫った。その時である。目蓋の裏に空と海の群青(ぐんじょう)の広がる真っ只中に、オリーヴの枝をかざして立つアフロディテノ完璧な姿があった。それはナポリのシヌエッサでもシラクーサのグラーチアでもなく、ましてマグダラのマリアでもない。真昼の光の泡立つ波間に現れ潮雫(しおしずく)に煌(きら)めく無垢な姿のアフロディテであった。オリーヴの樹海は繁くたわわに波打ち輝いた。一糸まとわぬ壮麗な姿のアフロディテは、だが、何故か恥じらうように目を伏せると樹海を分けて遠く走り去って行った。
抒庵